「生まれた後HIVに感染することにより、人間の体内の免疫システムが損傷を受け、外部からの病原体を撃退できなくなったり、体内で発生する異物(腫瘍や病原微生物の増殖)を排除する機能が働かなくなったことでさまざまな症状(悪性腫瘍や感染症)」が出た状態を示します。
1.性行為感染 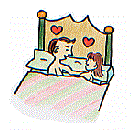
| 2.血液感染 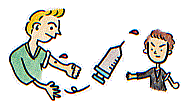
| 3.母子感染 
|
HIVが含まれている精液や膣分泌液、血液が、性器や肛門、口腔などの粘膜や、傷口に触れることで感染します。 | 注射の回し打ちや針刺し事故などにより、HIVが含まれている血液が体内に入ることにより感染します。 | 母親が感染していると、赤ちゃんに妊娠・出産・授乳を通して感染する可能性があります。 |
こんなことでは感染しません!!
軽いキス、食器の共用、同じ鍋をつつく、咳、くしゃみ、汗、トイレ、プール・風呂、握手、蚊やペットを介して
HIVは空気や水に触れれば死んでしまうほど弱いウイルスですので、日常の社会生活で感染をおそれる必要は全くありません。
HIVが人の体内に入ると、免疫を担当している細胞(ヘルパーT細胞)を集中的に攻撃して次々に破壊してしまいます。そのため体の抵抗力(免疫)がなくなり、健康な時にはかからないような、さまざまな感染症や悪性腫瘍(癌)などを引き起こします。
エイズになるまでの期間、いわゆる潜伏期間が非常に長いことがエイズの特徴です。
その後、全く症状のない状態が続きます。この時期の感染者を無症候性キャリアといい、血液中のヘルパーT細胞数は一定量以上保たれています。この期間の個人差は大きく、短い人で1年、長い人では10年以上と言われています。
ヘルパーT細胞がかなり減少してくると、エイズの前触れのような症状(リンパ腺の腫れ、1ヶ月以上続く発熱、持続性の下痢、体重の減少、全身のだるさ、寝汗等)がみられるようになります。
ヘルパーT細胞が一定量以下に減少すると、抵抗力がなくなり、日和見感染症(ニューモシスチス肺炎、食道カンジダ症等)や、カポジ肉腫などの悪性腫瘍、また脳症、認知症などの神経障害の症状が現れます。
いまのところ、からだの中のHIVを完全にとりのぞく治療法はありません。
しかし、HIVに感染しても、感染を早く知り、治療を早期に始め、継続することにより、エイズの発症を防ぐことで、感染していないときと変わらない日常生活を送ることができ、HIVに感染していない人と同じくらい長く生きられるようになりました。
HIV感染が判明したら、できるだけ早い段階で、抗HIV薬という、HIVの増殖を抑える薬の服用を開始すること(抗HIV療法)が勧められています。抗HIV療法が始まったばかりの頃は、1日数回、何錠もの薬を飲む必要がありましたが、今では1日1回1錠の服用で済む薬もあります。
また、治療を継続して体内のウイルス量が大きく減少すれば、HIVに感染している人から他の人への感染を防ぐことができます。
ただし、抗HIV薬はきちんと飲み続けないと、HIVが薬に対して耐性を獲得してしまい、薬が効かなくなってしまいます。いったん治療を開始したら、特別な場合を除き、治療を継続する必要があります。