いきもんネットとは?
いきもんネットとは?
熊本市の生きものや自然を守り、未来に引き継ぐため、生物多様性の保全や持続可能な利用に関する自主活動に取り組む市民活動団体や事業者、学校、行政機関などが情報を共有して、お互いに連携・協働し、活動等の情報を発信する制度として、「くまもとCひと・まち・いきもんネットワーク」(以下「いきもんネット」)を新たにつくりました。
いきもんネットについて、詳しくは下記のリンク先やちらしをご覧ください。
<いきもんネット詳細>
・リンク先:いきもんネットはじめました!!
いきもんネット登録者活動情報(一般参加募集イベント)
いきもんネット登録者活動情報(一般参加募集イベント)
いきもんネット登録者の生きもの、自然、生物多様性に関する活動の中で、一般の方に広く参加募集を呼びかけているものについて、下のリンク先に情報を掲載しています。
・リンク先:生きもの、自然、生物多様性関係のイベント
掲載中の情報の中で興味のある活動がありましたら、いきもんネット登録者に直接お尋ねください(連絡先は左記のいきもんネット登録者情報に掲載しています)。
いきもんネット登録者情報 (第1号 公益財団法人 再春館「一本の木」財団)
第1号 公益財団法人 再春館「一本の木」財団

○代表者:理事長 葉玉 匡美
○担当者:木庭 美津江
○連絡先:〒861-2201 熊本県上益城郡益城町寺中1363-1
TEL 096-289-4179、FAX 096-287-4612
メールアドレス ipponnoki@saishunkan.co.jp
○ホームページ(URL)、SNS等:https://ipponnoki.jp/
○団体等の構成人数:4人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 一本の木キッズクラブや親子の自然体験学習会による自然観察会の開催 等
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
次の4つの公益事業を実施しています。
(1)環境教育活動事業:
子どもたちに熊本の自然環境を学んでもらうための環境教育活動を行っています。
・再春館一本の木キッズクラブ
・親子の自然体験学習会
(2)普及・啓発事業:
熊本の自然や環境の保護保全に関する普及、啓発を促すための事業です。ホームページや
テレビCM、新聞などの広告媒体、書籍の発行や講演会による自然環境への啓発を行いま
す。
(3)助成事業:
熊本県内の自然環境の保護や保全に尽力している団体または個人への助成事業です。
環境整備・保全をはじめ、普及啓発や環境教育など、自然環境に関する活動を対象として
います。
(4)環境保全活動・環境整備事業:
地域の緑化・美化のために樹木の寄贈や管理を行う環境保全活動・環境整備事業です。
平成22年度から万日山への桜などの寄贈や管理を行い、平成24年度から第2空港線への
樹木の寄贈や管理を行っています。
○主な活動フィールド:
・山、森林、里地里山 ・市街地、公園 ・湧水地 ・河川・河川敷・水路
・海、干潟
○主な活動場所
・水前寺・江津湖 ・有明海(干潟) ・東区 ・西区
・その他(阿蘇管内、天草管内、益城町)
○活動頻度
・年間7~12回
〇活動報告書
 ・平成30年度 活動報告書(PDF:741.6キロバイト)
・平成30年度 活動報告書(PDF:741.6キロバイト)
 ・令和2年度 活動報告書(PDF:546.3キロバイト)
・令和2年度 活動報告書(PDF:546.3キロバイト)
 ・令和6年度 活動報告書(公益財団法人再春館一本の木財団)(PDF:106.3キロバイト)
・令和6年度 活動報告書(公益財団法人再春館一本の木財団)(PDF:106.3キロバイト) 
いきもんネット登録者情報 (第2号 立田山自然探検隊)
第2号 立田山自然探検隊

○代表者:会長 藤井 由幸
○担当者:益田 勝行
○連絡先:メールアドレス happa-green@xg8.so-net.ne.jp
○ホームページ(URL、SNS等):https://tatsudayamatankentai.com/ (外部リンク)
(外部リンク)
○団体等の構成人数:45人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略1(知る)に寄与する活動(野生動植物の調査等)
→ モニタリングサイト1000里地調査の実施 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 一般参加向けの自然観察会の開催 等
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
・熊本市の緑のオアシス「立田山」の自然に遊び、自然に学ぶ事を目的に、1987年から月例
の親子中心の自然観察会(デイキャンプ、ドングリ、トンボ、七草、歩け歩け等々)を
続けています。発足から30年余り。330回の例会を重ね、延べ13000人の皆さんとご一緒
に立田山を歩いてきました。
・団体等の依頼を受けて自然観察指導を行っています。
・日本自然保護協会が運営する「モニタリングサイト1000里地調査(環境省:一般サイト
《カエル類》」に参加しています。
・案内役は、(財)日本自然保護協会登録の自然観察指導員(地域の自然を守るボランティ
アリーダー)です。私たちは、県内の仲間たちと結成された「自然観察くまもと(自然観
察指導員熊本県連絡会)」に所属し県内各地で活動しています。
○主な活動フィールド:
・山、森林、里地里山
○主な活動場所
・立田山 ・北区 ・中央区
○活動頻度
・年間7~12回
〇活動報告書
 ・平成30年度 活動報告書
・平成30年度 活動報告書 PDF:883.8キロバイ
PDF:883.8キロバイ
いきもんネット登録者情報 (第3号 天明農地・水・環境保全管理協定運営委員会(天明環境保全隊))
第3号 天明農地・水・環境保全管理協定運営委員会(天明環境保全隊)

○代表者:会長 原田 正弘
○担当者:加藤 由香里
○連絡先:〒861-4125 熊本市南区奥古閑町1863-5
TEL 096-223-2226、FAX 096-223-5606
メールアドレス tenmei.hozen2007@gmail.com
○団体等の構成人数:約11,500人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略1(知る)に寄与する活動(野生動植物の調査等)
→ 護藤、三本松、中緑、銭塘・内田、奥古閑・海路口、川口地区の農地を中心とした
生きもの調査の実施 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 田んぼや水路の生きもの、自然の大切さを伝える出前講座の実施 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略3(守る)に寄与する活動(絶滅危惧種の保全、外来種対策等)
→ 外来水草及び外来タニシの駆除、水源かん養林の育樹 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略4(創る)に寄与する活動(生物多様性に配慮した緑化、環境作り等)
→ 農業排水路の整備に伴う魚巣ブロック及び水田魚道の設置 等
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
水路等地域資源の保全が困難となる中、協働組織を立ち上げ、非農家も含めた地域住民の保全活動を広域的に展開しています。
天明環境保全隊は、「魅力ある農村」「清らかな自然」「住み続けたいと思う生活環境」づくりを目指して、農地・農業用水路の保全、生態系、水質、生活環境、地下水等の保全活動に努めています。
○主な活動フィールド:
・山、森林、里地里山 ・田園地域 ・市街地、公園 ・河川・河川敷・水路
○主な活動場所
・南区
○活動頻度
・年間7~12回
〇活動報告書
 ・平成30年度 活動報告書(PDF:486.9キロバイト)
・平成30年度 活動報告書(PDF:486.9キロバイト)
いきもんネット登録者情報 (第4号 特定非営利活動法人 くまもとライフボート)
第4号 特定非営利活動法人 くまもとライフボート

○代表者:理事長 馬場 厚
○担当者:理事長 馬場 厚
○連絡先:〒861-3103 熊本県上益城郡嘉島町井寺2973
TEL 096-297-7151
メールアドレス entry_kashima@yahoo.co.jp
○団体等の構成人数:41人
○SNS等(URL) Facebook https://www.facebook.com/kumamoto.lifeboat
Instagram https://www.instagram.com/kumamotolifeboat
Twitter https://twitter.com/Life_Boat_kuma
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略1(知る)に寄与する活動(野生動植物の調査等)
→ 捕獲した魚類の記録 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 淡水生物の保全に関する勉強会・セミナー・イベントの開催 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略3(守る)に寄与する活動(絶滅危惧種の保全、外来種対策等)
→ 外来魚の駆除(張り網・たも網使用、釣り大会) 等
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
熊本市の江津湖地域に於いて、持続的な淡水生物の保全を目的として、在来種(魚)を保全するために、江津湖に流入する小河川の外来種(魚)の調査並びに捕獲・駆除活動を行う。
本地域に生息する外来種(魚)は、特定外来生物であるオオクチバス(ブラックバス)やブルーギルに加え、ティラピア・カムルチー(雷魚)等熊本市の条例で指定されている指定外来魚等により在来種(魚)に対する食害並びに生活の場所や餌を奪うなど、生態系に大きな影響を与えるおそれのあるものがいることから、捕獲並びに調査活動を行う。
また、一般市民に対して在来種の現状や保全の重要性を普及・啓発するために、淡水生物の保全に関する勉強会やセミナー、イベントなどを実施開催する。
今後の当該地域に於ける在来種保全を持続していくために小学校を対象として、環境学習のお手伝いや江津湖の生態系に関するパンフレットを作成し配布すると共に、一部の高校・大学・近隣住民等には外来種(魚)捕獲ボランティアとして参加を呼びかける。
将来的には、当活動を本地域全体での取組として行い、豊かな生物多様性を維持・継続させるために淡水生物の保全を目指す。
○主な活動フィールド:
・湧水地 ・河川・河川敷・水路
○主な活動場所
・水前寺・江津湖 ・東区 ・中央区
○活動頻度
・年間7~12回
〇活動報告書
 ・平成30年度_活動報告書(PDF:535.8キロバイト)
・平成30年度_活動報告書(PDF:535.8キロバイト)
いきもんネット登録者情報 (第5号 熊本県博物館ネットワークセンターミュージアムパートナーズクラブ 貝類調べ隊)
第5号 熊本県博物館ネットワークセンターミュージアムパートナーズクラブ 貝類調べ隊

○代表者:堀田 晃海
○担当者:堀田 晃海
○連絡先:メールアドレス eruminikoro_mi@yahoo.co.jp
○団体等の構成人数:15人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略1(知る)に寄与する活動(野生動植物の調査等)
→ 調査で確認された貝類の記録 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略3(守る)に寄与する活動(絶滅危惧種の保全、外来種対策等)
→ 外来種(貝類)の調査 等
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
<主な活動>
県内各地の陸産貝類の分布、岩礁や干潟の貝類を観察・調査し、棲息状況により、環境の変化などを記録する。
必要に応じ、標本を採集して保存する。
<参加者募集>
講師の専門家(貝類研究者)以外は、老若男女の素人の集まりです。ワイワイと楽しく、海や山に出かけて、大きな貝や極小サイズの貝類を探しています。
捜し物が好きな方、お待ちしています。
○主な活動フィールド:
・山、森林、里地里山 ・市街地・公園 ・海・干潟
○主な活動場所
・金峰山系 ・雁回山(木原山) ・有明海(干潟) ・西区 ・南区 ・北区
・その他(県内一円)
○活動頻度
・年間7~12回
〇活動報告書
いきもんネット登録者情報 (第6号 NPO法人 コロボックル・プロジェクト)
第6号 NPO法人 コロボックル・プロジェクト

○代表者・担当者:理事長 甲斐原 巖
○連絡先:〒860-0072 熊本市西区花園7丁目1752-18
TEL 090-2962-8668、FAX 096-351-5839
メールアドレス kaibara29@yahoo.co.jp
○ホームページ(URL、SNS等):
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012768818520
○団体等の構成人数:58人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略1(知る)に寄与する活動(野生動植物の調査等)
→ モニタリングサイト1000里地調査の実施 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 一般参加向けの自然観察会の開催 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略3(守る)に寄与する活動(絶滅危惧種の保全、外来種対策等)
→ 耕作放棄地の利活用 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略4(創る)に寄与する活動(生物多様性に配慮した緑化、環境作り等)
→ 成道川に生息する魚類等に配慮した河川整備の提言 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略5(活かす)に寄与する活動(エコツーリズム、地元農水産ブランドの推奨等)
→ 金峰山の自然・地下水、歴史、文化の魅力を活かした活動の推進 等
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
「自然を 楽しもう 知ろう 守ろう ~パートナーシップで~」をテーマに、金峰山系を主なフィールドにして
・「柿原迫谷の里」を中心に、モニタリング1000里地調査で中大型哺乳類やホタル・カヤネズ
ミなどの調査を実施。その結果を、自然観察会・体験活動として「コロボックル探検隊」(4
~6・8~10・12・2月)と「金峰山学講座」(4・5・2・3月)を継続しています。
・金峰森の駅「みちくさ館」横の不耕作地を整備。そこで、景観作物やエゴマ・もち米・野菜
の栽培と食育として「花・夢プロジェクト」(5・7~12・2・3月)を継続しています。
・諸活動に参加する多様な個性の子どもたち、その発達を支援するための子ども発達支援相談
センター主催の講座(月例)と「やんちゃキャンプ」(7月)を継続しています。
・これらの活動をもとに生物多様性の保全と持続可能な利用に向けて、パートナーシップの
もと数年に一度、「里山フォーラム」を実施しています。
○主な活動フィールド:
・山、森林、里地里山 ・田園地域 ・湧水地 ・河川・河川敷・水路
○主な活動場所
・金峰山系 ・西区 ・北区 ・その他(南阿蘇村(キャンプ))
○活動頻度
・年間12回以上
〇活動報告書
 ・平成30年度_活動報告書(PDF:1.39メガバイト)
・平成30年度_活動報告書(PDF:1.39メガバイト)
いきもんネット登録者情報 (第7号 自然観察指導員熊本県連絡会)
第7号 自然観察指導員熊本県連絡会

○代表者:会長 つる 詳子
○担当者:中間 幸弘
○連絡先:メールアドレス nakamafamily@jcom.zaq.ne.jp
○ホームページ(URL、SNS等):https://www.facebook.com/nature.kumamoto/
(fecebookのユーザー名が「自然観察くまもと」で表示されます。)
○団体等の構成人数:192人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略1(知る)に寄与する活動(野生動植物の調査等)
→ 河川の水環境調査 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 一般参加向けの自然観察会の開催 等
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
日本自然保護協会が主催する自然観察指導員講習会の受講者が集まって1982年にスタートした会です。会の目的は、自然観察を通して、自然に親しみ自然のしくみを知ることで自然保護の大切さを広めていくことです。自然観察指導員だけでなく、自然に興味をもつ多くの仲間により、自然観察会、調査、会報の発行、自然保護セミナー、研修会など様々な活動を続けています。
活動のフィールドは、熊本市内のみならず、阿蘇、天草、八代、人吉地域など熊本県内全域に渡っています。
熊本市内では、江津湖でのホタル観察会、立田山での自然観察会、市役所周辺での鳴く虫観察会、雑木林の自然観察会などを実施しています。
○主な活動フィールド:
・山、森林、里地里山 ・田園地域 ・市街地・公園 ・湧水地
・河川・河川敷・水路 ・海・干潟
○主な活動場所
・立田山 ・水前寺・江津湖 ・東区 ・中央区
・その他(阿蘇、八代地域ほか県内全域)
○活動頻度
・年間12回以上
〇活動報告書
 ・平成30年度 活動報告書(PDF:1.27メガバイト)
・平成30年度 活動報告書(PDF:1.27メガバイト)
いきもんネット登録者情報 (第8号 江津湖動植物観察会)
第8号 江津湖動植物観察会

○代表者:尾崎 友信
○担当者:尾崎 友信
○連絡先:メールアドレス oringsi@yahoo.co.jp
○団体等の構成人数:10人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略1(知る)に寄与する活動(野生動植物の調査等)
→ 自然観察会で観察された動植物のリスト化 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 自然観察会の開催 等
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
江津湖の自然を愛しているメンバーが集まり、月に1回程度江津湖を散策し、そのとき観察できた動物や植物を観察します。
これまで観察できた動植物をリストにまとめています。名前の分からないものなども、みんなで調べて勉強しています。
○主な活動フィールド:
・湧水地 ・河川・河川敷・水路
○主な活動場所
・水前寺・江津湖 ・東区 ・中央区
○活動頻度
・年間7~12回
〇活動報告書
 ・平成30年度 活動報告書(PDF:1.05メガバイト)
・平成30年度 活動報告書(PDF:1.05メガバイト)
いきもんネット登録者情報 (第9号 水と緑ワーキンググループ)
第9号 水と緑ワーキンググループ

○代表者:代表 大住 和估
○担当者:大住 和估
○連絡先:〒862-0955 熊本市中央区神水本町1-67
FAX 096-383-5919
メールアドレス tonerikosha@nifty.com
○ホームページ(URL、SNS等):https://www.facebook.com/mizutomidori/
○団体等の構成人数:60人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 水辺の生き物観察会の開催 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略3(守る)に寄与する活動(絶滅危惧種の保全、外来種対策等)
→ 冬水田んぼの利活用 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略5(活かす)に寄与する活動(エコツーリズム、地元農水産ブランドの推奨等)
→ 地下水を味わう野点カフェの開催 等
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
「生物多様性と私たちの暮らし」をテーマに行動を展開。
また、地下水保全の活動から、林業や農業、特に上流域の農業との連携を行っている。具体的には、地下水と農産物(経済)のささやかな循環で、活動時に何らかの形で農産物を提供する。
小学生と家族を対象に、江津湖での自然観察会と上流域の有機農業の田畑での観察会を交互に行っている。そして、そこの農産物を使ったものを観察会で提供している。農薬や化学肥料を使わない安心安全な農業は多様な生物を育み、安心安全な地下水につながることを体感してもらう。
【これまでの活動】
・バスツアー(水源から下流まで、みずみちを辿って)
・森に親しむ活動(間伐や下草刈り体験、蔓細工、焼き芋など、林野庁九州森林管理局との
協働で、林野庁が管理している山で体験)
・ムササビ観察会(熊本市西区、南区、中央区、山都町)
・ハクセンシオマネキ観察会(上天草市)
・コウモリ観察会(本妙寺洞窟)
・クロツラヘラサギ観察会(江津湖)
・ヒゴタイ観察会(産山村)
【現在不定期に行っている活動】
<自然観察会(上江津湖)>
・水質調査(CODキットを使用)
・水辺の生き物観察会
・野鳥観察会
・地下水を味わう野点カフェ
・江津湖の地質探検
<上流域の農家との連携>
・白川中流域の田んぼの学校参加
・冬水田んぼでの生き物観察会(益城町)
・田んぼとビオトープの生き物観察会(美里町)
○主な活動フィールド:
・山、森林、里地里山 ・田園地域 ・市街地・公園 ・湧水地
・河川・河川敷・水路 ・海・干潟
○主な活動場所
・雁回山(木原山) ・水前寺・江津湖 ・西区 ・南区 ・中央区
・その他(山都町、上天草市、八代市、産山村、益城町、美里町など)
○活動頻度
・不定期
〇活動報告書
いきもんネット登録者情報 (第10号 水前寺江津湖公園サービスセンター)
第10号 水前寺江津湖公園サービスセンター

○代表者:所長 今林 則隆
○担当者:尾崎 友信
○連絡先:〒862-0906 熊本市東区広木町935-1
TEL 096-360-2620
FAX 096-288-9852
メールアドレス sakabe_t@ezuko-park.com
○ホームページ(URL、SNS等):http://www.ezuko-park.com/
○団体等の構成人数:5人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 自然観察会の開催 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略3(守る)に寄与する活動(絶滅危惧種の保全、外来種対策等)
→ 希少植物の保全や外来水草の駆除作業 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略4(創る)に寄与する活動(生物多様性に配慮した緑化、環境づくり)
→ カイツブリの営巣や魚類等の生息空間に配慮した外来水草の駆除 等
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
(1)ライフステージに応じた自然を学ぶ体験学習プログラム
水前寺江津湖公園では、幼児からシニア年齢層まで、それぞれのライフステージで楽しめる
環境学習プログラムの提供を行っています。
(2)希少植物の保護 ~市民協働による保全活動~
水前寺江津湖公園では、ミズアオイやキタミソウ等の絶滅危惧種の保全活動にも取り組んで
います。
保全管理には専門的な知識や経験が必要なことから、江津湖の動植物に精通した専門スタッフ
「江津守(えづもり)」を配置するとともに、市民ボランティアとも連携して、市民協働での
保全活動を行っています。
(3)生物生息環境に配慮した植物管理、湖面管理
陸地と水域の境界において生物生息環境が連続的に変化する「水辺のエコトーン」に配慮した
選択的草刈や、カイツブリの営巣や魚類等の生育空間にも配慮した水草除去作業など。また、
ブラジルチドメグサやナガエツルノゲイトウなどの外来水草の駆除作業も行っています。
○主な活動フィールド:
・市街地・公園 ・湧水地 ・河川・河川敷・水路
○主な活動場所
・水前寺・江津湖 ・東区 ・中央区
○活動頻度
・年間12回以上
〇活動報告書
 ・平成30年度_活動報告書(PDF:494.7キロバイト)
・平成30年度_活動報告書(PDF:494.7キロバイト)
いきもんネット登録者情報 (第11号 熊本県シェアリングネイチャー協会)
第11号 熊本県シェアリングネイチャー協会
○代表者:理事長 福本 寿太郎
○担当者:小嶺 仁
〇連絡先:メールアドレス ori☆minamata-nature.com
メールアドレス(担当者)komikomi0419☆yahoo.co.jp
「ご連絡の際は☆を@に変えてください」
電話番号(担当者) 090-4351-6954
○ホームページ(URL、SNS等):
https://www.facebook.com/XiongBenXianshearinguneichaneichagemuXieHui/
○団体等の構成人数:150人
○活動内容:
熊本市生物多様性戦略※の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→自然ふれあい体験学習の実施
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
熊本県シェアリングネイチャー協会は公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会に所属をしております。
ネイチャーゲームは、1979年米国のナチュラリスト、ジョセフ・コーネル氏により発表された活動で、見る・聞く・触る・嗅ぐなど、さまざまな感覚を使って、自然とふれあい、感動し、自然の持つさまざまな表情を楽しみ、その体験を分かち合う環境教育プログラムです。自分の感性を活かして、「自然への気づき」が深まることを大切にしています。四季折々にどなたでも自然とのふれあい体験ができます。
熊本県の活動は全県に6つの地域の会があり、それぞれの地域で活動をしております。熊本市内はくまもとシェアリングネイチャーの会やくすの木シェアリングネイチャーの会が担当しており、2019年度は立田山での活動や江津湖、龍田プレイパークにて活動をしています。
○主な活動フィールド:
・山、森林、里地里山 ・田園地域 ・市街地・公園 ・河川・河川敷・水路 ・海・干潟
○主な活動場所
・立田山 ・水前寺・江津湖 ・東区 ・北区 ・中央区 ・その他(甲佐町・宇土市・水俣ほか県内全域)
○活動頻度
・年間3~6回
○活動報告
いきもんネット登録者情報 (第12号 熊本野生生物研究会)
第12号 熊本野生生物研究会
登録年月日:2021年4月9日

○代表者:会長 坂田 拓司
○担当者:事務局長 天野 守哉
〇連絡先:メールアドレス jimukyoku@kumayaken.org
○ホームページ(URL、SNS等):
https://kumayaken.org/
○団体等の構成人数:74人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略1(知る)に寄与する活動(野生動植物の調査等)
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略3(守る)に寄与する活動(絶滅危惧種の保全、外来種対策等)
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
哺乳類を中心とした野生生物の調査研究や環境教育に35年間取り組み、その成果は会誌
や本の出版などを通して情報提供している。絶滅危惧種や特定外来生物の生息状況を把握
し、その対策に講じるとともに行政への提言も行っている。
1 会員研究発表会
(1)「熊本県天草市近海から得られた熊本県初記録を含む魚類」「九折瀬洞の動物を探る」
「江津湖協議会環境部会について」「熊本県内のアライグマの現状」
「熊本県内での重症熱性血小板減少症候群(SFTS)ウイルス調査」
(2)「熊本県内におけるトラップを用いたコテングコウモリの生息確認記録「人吉海軍航空隊跡
地のコウモリ」「熊本県内アライグマ調査報告」「山都町観察会報告」「矢部郷自然」
2 談話会(講演会)
講演「江津湖の生き物について」 熊本博物館展示室見学 熊本城コウモリ観察会
3 観察会 ムササビとゲンゴロウ観察会(山都町男成神社)
4 RDB補完調査協力
(1)コウモリ調査 (2)カモシカ調査 (3)外来生物(クリハラリス・アライグマ)の情報収集
(4)RDBくまもと2019の執筆
5 カモシカ特別調査協力
6 機関誌SIGN POST発行 年間4号
7 会員メーリングリストやWEBサイト等の運営
8 その他
(1)会員や所属団体の活動に対する協力 (2)熊本県自然保護関係団体協議会
(3)クリハラリス仮剥製制作研修会の実施
・出版物:
学術誌「熊本野生生物研究会誌」1~10号
30周年記念「くまもとの哺乳類」(東海大学出版部 2015年)
・受賞歴:
くまもと環境賞(2005年 2020年) 熊日出版文化賞(2016年)
「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰(2016年)
○主な活動フィールド:
・山、森林、里地里山 フィールドを定めることなく活動
○主な活動場所
・熊本市を含む県内全域
○活動頻度
・不定期
いきもんネット登録者情報 (第13号 大和リース株式会社 熊本支店)
第13号 大和リース株式会社 熊本支店
登録年月日:2021年7月20日

○代表者:支店長 杉 武
○担当者:相馬 美代
○連絡先:メールアドレス soma@daiwalease.jp
電話番号 096-375-0120
FAX番号 096-375-0121
○ホームページ(URL、SNS等):
https://www.daiwalease.co.jp/
○団体等の構成人数:31人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略4(創る)に寄与する活動(緑化、生物多様性に配慮した環境作り等)
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
当社は、事業活動のひとつとして緑化事業を行っています。緑化事業で扱っている商品は、建物の壁面、室内、屋上など様々な場面に対応し、緑化を創出しています。また、空気の浄化作用やヒートアイランド現象の緩和など環境の改善に効果を発揮しています。
二酸化炭素の排出量の抑制→熊本の生物多様性の環境創りへと貢献できるよう熊本支店の事務所にも緑化商品を設置しています。
熊本支店独自の取組としては、危険・音がうるさい等のイメージを持たれやすい建設現場に、熊本支店の社員が作成した生物多様性や環境に関するクイズを掲示する活動を行っています。この活動で次のようなメリットをもたらすことが出来ると考えています。
◆当社…環境に対する関心を持つキッカケとなる
生物多様性の知識を身に付けることができる
建設現場へのイメージを変える
◆地域住民…環境に対する関心を持つキッカケとなる
◆地域の子どもたち…クイズが最近のブームということもあり、
楽しみながら環境へ関心を持つことができる
実際に、社員がクイズを作成する段階で、「意外と知らないことがたくさんあった」
「調べてみるとおもしろい」という声を聞くことができました。
2021年4月より、熊本市西区花園の建設現場に設置しています。
”クイズを作成する”という工程に取り組むためには、必ず地球環境や熊本の環境についての知識を身に付けておく必要があります。
今後の活動として、当社からの一方的な掲示ではなく、地域の方々も一緒に参加して環境への関心を持つキッカケ作りとなるようなツール作成・取組み(地域の方がクイズを作成・応募して当社が掲示する 等)を取り入れていこうと考えています。
○主な活動フィールド:
・市街地、公園、当社が担当する建設現場など
○主な活動場所
・熊本市を含む県内全域
○活動頻度
・年間1~2回
〇活動報告書
いきもんネット登録者情報 (第14号 江津湖研究会)
第14号 江津湖研究会
登録日:2021年9月3日
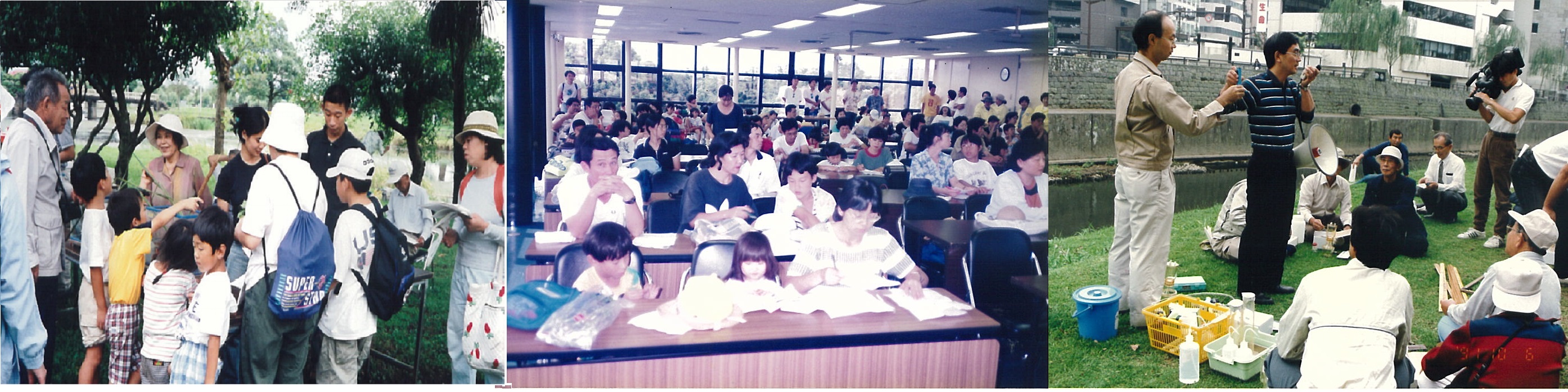
○代表者:会長(東海大学名誉教授)椛田 聖孝
○担当者:椛田 聖孝
〇連絡先:メールアドレス kkabata@agri.u-tokai.ac.jp
電話番号 096-293-6403
FAX番号 096-293-6403
○ホームページ(URL、SNS等):
https://www.ezuko-research.com (外部リンク)(現在休止中)
(外部リンク)(現在休止中)
https://www.sigen-kyousei-research.com/ (外部リンク)(現在休止中)
(外部リンク)(現在休止中)
○団体等の構成人数:20人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略1(知る)に寄与する活動(野生動植物の調査等)
→ 江津湖の生態系調査 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 一般参加向けの自然観察会の開催 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略3(守る)に寄与する活動(絶滅危惧種の保全、外来種対策等)
→ 阿蘇地域の資源保全 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略4(創る)に寄与する活動(緑化、生物多様性に配慮した環境作り等)
→ スイゼンジノリの養殖・成分研究 等
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
本会は江津湖を熊本水環境のシンボルとして捉え、その上流域を含め、自然環境保全に役立つ活動を行っています。令和3年で創立40年。熊本市動植物園との共催で、30年に亘り親子自然観察会を開催。令和1年、令和2年はコロナ禍のため中止。熊本県文化協会、環境文化部会と共催で講演会当を開催しています。
また、日本固有種であるスイゼンジノリの保全活動等を30年に亘り行っています。
○主な活動フィールド:
・市街地、公園、河川・河川敷・水路
○主な活動場所
・水前寺・江津湖、白川・緑川、その他に熊本市上流域の阿蘇等
○活動頻度
・年間3~6回
〇活動報告書
いきもんネット登録者情報 (第15号 立田山野外保育センター(雑草の森))
第15号 立田山野外保育センター(雑草の森)
登録日:2021年9月29日

○代表者:センター長 西島 徹郎
○担当者:山戸 知子
○住所:熊本市北区龍田陳内1丁目5番66号
〇連絡先:メールアドレス zassounomori@kuma-shiho.jp
電話番号 096-348-7300
FAX番号 096-339-7123
○ホームページ(URL、SNS等):
雑草の森ホームページ (kumashiho.jp)
○団体等の構成人数:4人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 未就学児童向けの自然観察会の開催 等
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
【基本方針】
立田山野外保育センター(雑草の森)は、就学前の児童をはじめ、多くの方々に利用いただき、平成14年の開設以来、26万人を超える皆様に利用いただいております。
センターでは、保育園や幼稚園の日帰り活動、宿泊体験の場を提供するとともに、立田山の豊かな自然の中で、森の生き物や小鳥たち、そして草花とふれあい、のびのび遊び、自然への畏敬の念と思いやりの心をもった子どもを育てるための事業にも取り組んでいます。
【自主事業】
春の自然楽校、夏の自然楽校、冬の自然楽校、まごマゴキャンプ、
親子キャンプ、わんぱくまつり、雑草の森まつり
○主な活動フィールド:
・山、森林、里地里山
○主な活動場所
・立田山
○活動頻度
・年間7~12回
いきもんネット登録者情報 (第16号 NPO法人くまもと未来ネット)
第16号 NPO法人くまもと未来ネット
登録日:2022年9月20日
写真準備中
○代表者:代表理事 原 育美
○担当者:歌岡 宏信
○住所:熊本市東区江津1丁目7-17
〇連絡先:メールアドレス home@kumamoto-mirai.com
電話番号 096-362-3776
FAX番号 096-200-6395
○ホームページ(URL、SNS等):https://kumamoto-mirai.com/
○団体等の構成人数:9人(理事)、会員は多数
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略1(知る)に寄与する活動(野生動植物の調査等)
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 江津湖等における環境学習事業 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略3(守る)に寄与する活動(絶滅危惧種の保全、外来種対策等)
→ 鳥獣害対策実行支援(主にアライグマ防除研修) 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略4(創る)に寄与する活動(生物多様性に配慮した緑化、環境作り等)
→ 地下水涵養に関する各種事業 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略5(活かす)に寄与する活動(エコツーリズム、地元農水産ブランドの推奨等)
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
当会は、1994年に「環境ネットワークくまもと」としてスタートし、2016年の熊本地震という大きな体験を経て、”熊本を持続可能な地域とするには”という課題を再確認し、これまでの環境系の活動を継続すると共に、発展的な改組を行い、NPO法人『くまもと未来ネット』として現在の活動を繋いでいます。
多様な活動を整理し具体化するため以下の4つのプロジェクトを中心に活動をしていますが、その中の下記プロジェクトが該当する活動であると考えています。
中山間地の暮らしを守り、水資源を育む「生物多様性プロジェクト」
豊かな里山、そして水資源は人々の営みの中で守られてきました。しかし、近年の少子高齢化や人口減少などにより、その環境は大きく変わりつつあります。鳥獣害被害、そして、特定外来種被害は深刻さを増しています。このような中で地域の豊かさと、生物多様性、そして水資源を守る活動を行います。
具体的事業内容
● 鳥獣害対策実行支援(主にアライグマ防除研修)
● 地下水涵養に関する各種事業(白川中流域の涵養活動、水サミットへ参加)
● 江津湖等における環境学習事業
○主な活動フィールド:
・山、森林、里地里山 ・田園地域 ・市街地、公園 ・湧水池 ・河川、河川敷、水路
○主な活動場所
・金峰山系 ・立田山 ・雁回山 ・水前寺、江津湖 ・白川、緑川 ・有明海(干潟)
・その他(白川中流域、流域の上流から下流まで、県内各所)
○活動頻度
・年間3~6回
いきもんネット登録者情報 (第17号 日本野鳥の会熊本県支部)
第17号 日本野鳥の会熊本県支部
登録日:2023年7月6日

○代表者:支部長 田中 忠
○担当者:原口 研治
○住所:熊本市北区八景水谷3-7-38
〇連絡先:メールアドレス rinbai@aries.zaq.jp
電話番号 096-346-0010
FAX番号 096-346-0010
○ホームページ(URL、SNS等):https://torikuma.com/
○団体等の構成人数:350人
○活動内容:
・熊本市生物多様性戦略※の基本戦略1(知る)に寄与する活動(野生動植物の調査等)
→ モニタリングサイト1000調査、全国鳥類繁殖分布調査、アオバズク繁殖調査、
ツバメの塒調査、タカ類の渡り調査、上江津湖と下江津湖でのカモ類など
水鳥の羽数調査、ツル類調査、クロツラヘラサギ・ズグロカモメ一斉調査、
熊本市市街地のミヤマガラス、ムクドリ、コムクドリのねぐら調査 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略2(学び、つながる)に寄与する活動(自然観察会の開催等)
→ 県内各地での探鳥会、子ども向けバードウォッチングの指導 等
・熊本市生物多様性戦略の基本戦略3(守る)に寄与する活動(絶滅危惧種の保全、外来種対策等)
→ 鳥に関する出版事業「熊本県の野鳥」1978年5月発行
「くまもとの野鳥(写真図鑑)」2009年9月発行
「熊本県鳥類誌(熊本県産鳥類目録)」2016年8月発行、
行政等の自然保護活動への参画、第一回熊本環境賞受賞
○詳細な活動内容や団体等のPRポイント:
当会は、1969年1月15日「野鳥に関する知識と愛護思想の普及、調査研究」などを目的に「熊本野鳥の会」として設立され、1982年に「日本野鳥の会熊本県支部」へと名前を変更、2019年には50周年を迎えております。
○主な活動フィールド:
・山、森林、里地里山 ・田園地域 ・市街地、公園 ・湧水池 ・河川、河川敷、水路
・海、干潟
○主な活動場所
・金峰山系 ・立田山 ・雁回山 ・水前寺、江津湖 ・白川、緑川 ・有明海(干潟)
・東区 ・西区 ・南区 ・北区 ・中央区
○活動頻度
・年間12回以上
※第2次熊本市生物多様性戦略(令和6年3月策定)
本市では生物多様性を保全し、将来にわたってそのめぐみを受け続けていくことに向けた、市民、市民活動団体、事業者、行政等、熊本市の全ての主体の行動の指針となる基本計画として、平成28年3月に策定した「熊本市生物多様性戦略~いきもん つながる くまもとCプラン~」を改定し、令和6年(2024年)3月に「第2次熊本市生物多様性戦略」を策定しました。
この戦略では、生物多様性とはどのようなものか、熊本市における生物多様性の現状と課題、熊本市が目指す望ましい姿を示し、その実現に向けた基本戦略と行動計画などを記載しています。
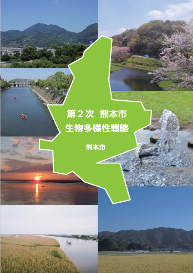
第2次生物多様性戦略
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
・熊本市生物多様性戦略